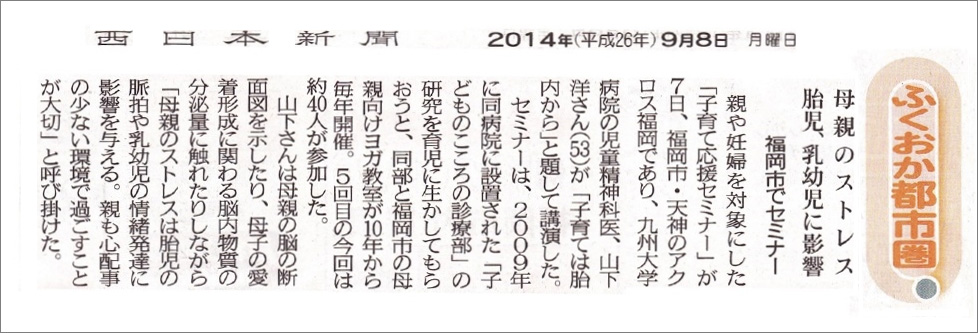子育てで一番大切なこととは、“あなたは価値がある存在なんですよ”ということを幼いころ(できればおなかのなか)から伝えること。なぜそれが大切なのか、どのようにしたらうまく伝えられるのか、子どもとの毎日が楽しく感じられますようにとの願いをこめて、山下洋先生がわかりやすくお話ししてくださる大人気のセミナーです。

イライラ、もやもや・・・育児にストレスはつきものですがひとりで抱え込んでいませんか?妊娠中のお母さんのストレスはおなかの赤ちゃんのストレスホルモンも増加させ先天異常や発育不全、早期産、生後の行動上の問題にまで影響を与えてしまいます。お母さんが心身ともに安定して妊娠期を過ごすことがいかに大切かということに気付かされます。子育てを楽しめてない方や、妊娠中の方はもちろん、妊娠や結婚を考えていらっしゃる方や、子育てに関心がある方、ご参加をお待ちしています!
ブログでは毎年のセミナーの様子»を一覧で掲載しておりますので是非ご覧くだい。

わたしは1993年から3年間、NHK九州厚生事業団が主催する「ことばの発達相談会」での相談講師を務めていたころ、同じ相談講師として山下先生と、年に4回一緒にお仕事をさせていただいていました。そのご縁で、カウンセリングのクライアントを山下先生に診ていただいたことも。
2008年、うつの体験を聴く勉強会をしたとき、山下先生にコメンテーターをお願いした際に快く承諾してくだり、うつや心の健康についてわかりやすくお話してくださいました。2009年夏、福岡県・新生活産業室の主催でシーズ発表会がありました。最初は「シーズ」という意味もよくわからないまま参加していたのですがいろいろな大学の先生方の発表を聴いているうちに、「シーズ」とは「種子」だとわかったのです。大学で研究されて産み出された種子を、産業界が一緒に育てていくのが、産学連携。サンシャインも、九州大学病院子どものこころの診療部で産み出された種子を一緒に育てていきたいと名乗りでました。山下先生は診療でお忙しいため実現は難しいと思っていた矢先、2010年に第1回産学連携セミナーが実現いたしました。
福岡県と新生活産業くらぶFUKUOKAの共催事業「産学連携新生活産業促進事業」から生まれた、九州大学とサンシャインの連携によるセミナー。「産後うつ」や「子どものうつ」を予防し、楽しく子育てしていくヒントについてのお話、妊娠中・子育て中の方、結婚・出産を考えている方、助産師・看護師・保育士さんなどにもおすすめの講座です。
講演テーマ:子育てにメンタライジングを活かす»
サンシャイン講座:「メンタライジング」の実践に役立つ呼吸法と瞑想を紹介します~
チラシ:「親子関係を深める極意を子どもの心の専門医から学ぶ」»
講演テーマ:子育てのメンタライジング»
サンシャイン講座:「メンタライジング」を助けるヨガの呼吸法と笑いヨガを紹介します~
チラシ:「親子の絆を深める極意を子どもの心の専門医に学ぶ」»
講演テーマ:自分らしい育児のススメ»
サンシャイン講座:自分らしさ ~私が教員時代に担当したある親子の事例紹介(1992.1.21.西日本新聞掲載)~
チラシ:「子育てがもっと楽しくなるヒミツを子どもの心の専門医がお教えします」»
講演テーマ:子どもを知ると育児はもっと楽しくなる!»
サンシャイン講座:育児が楽しくなる笑いヨガ
チラシ:「子どもの心の専門医が若いお母さんたちにいま伝えたいこと」»
講演テーマ:育児ストレスとさようなら»
サンシャイン講座:ストレスを解消するヨガの呼吸法と笑いヨガ紹介
チラシ:「現場の医師が教える、育児ストレスとの向き合い方」»
講演テーマ:子育ては胎内から»
当日プログラム:「概要「子どもと楽しく関わる為のストレスマネジメント」»
講演テーマ:最新脳科学を学んでポジティブ育児»
チラシ:「子育てがもっと楽しくなる脳科学」»
講演テーマ:子どもの自尊心を育む子育て»
サンシャイン講座:簡単にできるリラックス法(今月出産予定のマタニティヨガ生2人と一緒に)
チラシ:「もう子育てに悩まない!たった1つのこと」»
講演テーマ:絆をはぐくむ子育て»
サンシャイン講座:ハルちゃんママの胎内でのお話
当日プログラム:「概要「哲学する赤ちゃん」»
講演テーマ:子どものこころの育ちと家族のメンタルヘルス»
当日プログラム:新生活産業応援メールマガジン第46号»

医療の現場で、1993年から子どものこころや発達の問題に取り組まれている児童精神科医です。
九州大学病院 子どものこころの診療部 特任准教授・医学博士。専門分野は児童青年期精神医学。
「子どもは小さな科学者」と語るとおりの、子どもの能力や発達を子ども目線で見ることができる子どもの心のプロフェッショナル。厚生労働省・文部科学省研究費により産後うつ病・児童虐待の予防・介入に関する研究を行い、子どもの発達に関する母子相互作用や母親の心の問題についての臨床研究にも力を注がれており、親の気持ちも分かってくれる心強い味方でもあります。
2014年(第5回)当日、西日本新聞社の記者の方からの取材を受け翌日記事が掲載されました。